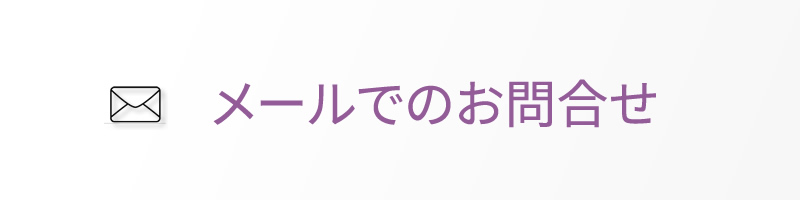お知らせ
10.172025
2025年10月法改正「柔軟な働き方を実現するための措置等」義務化スタート ―制度を“使える形”にできていますか?

2025年10月1日から、改正育児・介護休業法が施行されました。
今回の改正では、「3歳以上〜小学校就学前の子を養育する社員」に対して、
柔軟な働き方を実現するための措置を整備することが企業に求められます。
この改正は「制度を新たに設ける」だけでなく、
職場で実際に使える運用体制を整えることが重要なポイントです。
就業規則の改定だけで止まっていないか、次の3点を中心に一緒に確認してみませんか?
① 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の整備(2つ以上の措置から選択制)
企業は、次の5つの選択肢の中から2つ以上を整備し、社員が1つを選べるようにする必要があります。
- 始業・終業時刻の変更(勤務開始・終了時刻を一定期間変更できる制度)
- テレワーク等(所定労働時間を変更せず、月10日以上利用可能)
- 保育施設の設置・運営等(事業所内保育や外部施設との提携など)
- 養育両立支援休暇(所定労働時間を変更せず、年10日以上取得可能)
- 短時間勤務制度(原則1日6時間とする措置を含む)
このうち、どの措置を整備するかは企業の裁量ですが、選定内容を就業規則や関連規程に明記し、申出先・手続方法を社内で周知することが必要です。
特に、制度を導入したものの「誰に申し出るのか」「どのように申請するのか」が決まっていないケースは、実務上、見落としが生じやすいポイントです。
② 個別の周知と意向確認の実施
企業は、子が1歳11か月〜2歳11か月の間にある社員に対して、柔軟な働き方制度や所定外労働の制限などの内容を個別に周知し、意向を確認する義務があります。
この義務は、新しく導入した制度について、現に育児休業中の従業員に「3歳以降も利用できる制度がある」ことを確実に周知することを目的としています。
周知方法は、面談(オンラインを含む)、書面交付、メールやFAXなど、柔軟な対応が可能です。
③ 制度利用時の現場運用ルール整備
柔軟な働き方を実現するための措置は、現場での人員配置・業務分担の再設計が伴います。
短時間勤務者や養育両立支援休暇の利用が増えると、時間単位もしくは日によって人手不足が発生する可能性があります。
代替要員の確保や引継ぎ等をあらかじめ整備しておくと、制度利用時の混乱を防げます。
■ まとめ:再チェック!
就業規則の改定を済ませた皆さまも、以下の3点をいま一度チェックし、
社内の仕組みが実際に機能する状態になっているか確認してみましょう。
- ✓ 措置の選択:社員が2つ以上の措置の中から一つを選択できるようになっていますか。また、規程類に明文化されていますか。
- ✓ 個別周知の体制:対象者への個別周知・意向確認の流れや担当者は決まっていますか。
- ✓ 現場運用:引継ぎや業務分担について、整備できていますか。
育児休業中の給付金は、「どの制度で、いつ、いくらもらえるのか」正直わかりづらいですよね。
弊所では、育児休業の制度と各種給付金の関係を一目で整理した資料をご用意しています。
ご希望の方は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
【参考】
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
最近のお知らせ
-
2026/1/15
-
2026/1/8
-
2025/12/23
-
2025/12/6
-
2025/11/5
-
2025/10/28